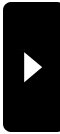2017年02月28日
さらっと研修が終わって、さらっと明日を迎えそう。
3年間続いたりんご作りの研修が、今日、終わった。
さらっと、この日を迎え、さらっと、明日を迎えそうな感じ。
これが独立ってやつか。
思っていたよりも、すごく、さらっとしている。
明日からは師匠に着かず、ひとりで畑に出ることになるんだ。
卒業だなんて、なんだか群れたアイドルっぽいじゃないか。研修生はひとりだったけれど。
。。。気持ちがさらっとしすぎているので、ブログでくらい、少し重みを出しましょう。
師匠の岩垂さんには3年間本当にお世話になった。
農業を何も知らない変な人間を雇ってくれて、一緒に作業しながら技術をひとつひとつ教えてくれた。
ありがとうございました。
俺も3年かけて徐々に成長してきた(はず)とはいえ、人件費の費用対効果なんて考え出したら何も言えなくなってしまう。
感謝しきれないので、今日の仕事終わりも日常に毛が生えたくらいで、さらっと帰ってきた。
まあ、今後も近くの畑にいるのだし、頻繁に顔を合わせることになる。
これからは同じ地域の農業者として、末永くよろしくお願いいたします。

さてこちらは、3年間お世話になった師匠の岩垂さんから貸していただく予定の畑。
こんなに良い、生り期(そんな言葉あるかわからんけど)の畑を貸していただけるなんて、どれだけありがたいことか。
親父さんの代からりんごを作り続けてきた畑だ。
俺は3年間、この畑で育った美味しいりんごを食べてきた。
この畑で、美味しいりんごが作れない、なんてことの無きよう。
ましてや、手が回らずに荒らしてしまった、なんてことの無きよう。
今日も明日も、一日中畑でりんごの木と向かい合うことは変わらないのだけれど、どうしても節目だ。
一旦、気を引き締めて、明日からまたがんばろう。
正式には明日から独立経営開始ってことになるのかもしれないけれど、気分的に4月1日からにしようと思っている。
だから1ヶ月の準備期間って感じか。(正直、いろいろ整っていないのだ)
てことで、このブログのタイトルやリード文も、あと1ヶ月はこのままの予定。
でも、予定は未定。
応援してくださったみなさん、ありがとうございました。
そして、これからもよろしくお願いします。
然
さらっと、この日を迎え、さらっと、明日を迎えそうな感じ。
これが独立ってやつか。
思っていたよりも、すごく、さらっとしている。
明日からは師匠に着かず、ひとりで畑に出ることになるんだ。
卒業だなんて、なんだか群れたアイドルっぽいじゃないか。研修生はひとりだったけれど。
。。。気持ちがさらっとしすぎているので、ブログでくらい、少し重みを出しましょう。
師匠の岩垂さんには3年間本当にお世話になった。
農業を何も知らない変な人間を雇ってくれて、一緒に作業しながら技術をひとつひとつ教えてくれた。
ありがとうございました。
俺も3年かけて徐々に成長してきた(はず)とはいえ、人件費の費用対効果なんて考え出したら何も言えなくなってしまう。
感謝しきれないので、今日の仕事終わりも日常に毛が生えたくらいで、さらっと帰ってきた。
まあ、今後も近くの畑にいるのだし、頻繁に顔を合わせることになる。
これからは同じ地域の農業者として、末永くよろしくお願いいたします。

さてこちらは、3年間お世話になった師匠の岩垂さんから貸していただく予定の畑。
こんなに良い、生り期(そんな言葉あるかわからんけど)の畑を貸していただけるなんて、どれだけありがたいことか。
親父さんの代からりんごを作り続けてきた畑だ。
俺は3年間、この畑で育った美味しいりんごを食べてきた。
この畑で、美味しいりんごが作れない、なんてことの無きよう。
ましてや、手が回らずに荒らしてしまった、なんてことの無きよう。
今日も明日も、一日中畑でりんごの木と向かい合うことは変わらないのだけれど、どうしても節目だ。
一旦、気を引き締めて、明日からまたがんばろう。
正式には明日から独立経営開始ってことになるのかもしれないけれど、気分的に4月1日からにしようと思っている。
だから1ヶ月の準備期間って感じか。(正直、いろいろ整っていないのだ)
てことで、このブログのタイトルやリード文も、あと1ヶ月はこのままの予定。
でも、予定は未定。
応援してくださったみなさん、ありがとうございました。
そして、これからもよろしくお願いします。
然
2017年02月27日
おくるみを作ってみた
またまた作ってみたシリーズです。
ベビー用品で何を作るか、ランキング的なものだと
ダントツ1位は「スタイ」。。。らしいですが
それに続いて比較的作る人が多そうなのが「おくるみ」。
ランチョンマットとかコースターとかのように
布2枚を中表に縫い合わせればほぼ完成!という手軽さゆえでしょう。

サイズは90センチ四方、
頭入れるっぽいところ用に
22センチの正方形を三角に折ったものを取り付けてみた。
そこに縫いしろ1.5センチを見ておく。
そうやって裁断して
三角形を挟み込んだ上で中表に縫い合わせる。
表に返しておさえミシンして・・・
・・・なんと単純!
なのですが、意外と苦戦したのが布選びと裁断です。
どういうのがいいのか?と考え出すといろんなパターンがあって
決められず。
薄すぎても厚すぎてもいけない?
結局は、赤ちゃんに触れる方をワッフル生地にして
表面はWガーゼにしました。
どちらも、ネットで購入。(ガーゼ生地って可愛いのはなかなか店頭にない)
どちらもあらかじめ水通しをしておきます。
届いたばかりのガーゼは、ホントにガーゼ?って不安になるような
ごわつきがあって驚きましたが
水を通すとフワフワになりました。よかった。
で、地味に苦労したのは、ワッフル生地の裁断。
凸凹があって、うまく線がひけないのです。
新聞紙で90センチ四方の正方形を作って、
それをマチ針でとめて縫いしろ多めに見て雑に裁断して、
結局は比較的キレイに裁断できたガーゼ生地と合わせた後に
余分な縫いしろを切り落とすという荒技でしのぐ。
そもそも、こういうシンプルな正方形とか長方形のモノを作る場合、
普通は型紙用意するのかな?それとも定規ではかるだけ?
・・・少なくとも、サイズが大きくなる場合は
やっぱり簡単な紙切れでもいいので
型紙があった方がやりやすい!というのが私の結論です。
適量の返し口を残して中表で縫ったあと、表に返すのですが
縫いしろを両サイドに割ってちゃんとアイロンをかける、
というのが実は大切だと気付く。
そして返し口は手縫いで「コの字」縫い。(←意外と手芸本には書いてないのだ!)
それから押さえミシン(←表から、縁のごく際部分をミシンで縫う)をかければ
一応完成!
・・・ここからついつい欲が出てしまう。
最初はパイピングしようかと思っていたのですが
頭のポケットにつけたレースが意外と気に入り
ナチュラルな感じのレースで縁取ることに。
90センチ四方なので結構な長さが必要です。
レースの継ぎ接ぎの仕方は謎だらけで
仕上がりもギリギリという感じですが何とかできました。
中表に縫うという技法にちなんで
オムツ替えで使えそうなシートも作ってみました。

45センチ×70センチ。
同じくワッフル生地に、こちらはナイロン生地(エコバッグのようなイメージ)を合わせて防水(?)に。
こちらは王道の、バイアステープでパイピング。
レース縫い付けるより、やり方が色々検索できるのもあって
苦戦しなかったな・・・。
いや、パイピングは以前練習したからかな?
単純作業でも、やってみると本には書かれていないような
細かい疑問が実はでてくるものです。
そこは試行錯誤の繰り返し。
とりあえず出来てよかった!という安堵はもちろんのこと、
ソーイングについてまたひとつ勉強になりました、
という思いです。
sachiko
ベビー用品で何を作るか、ランキング的なものだと
ダントツ1位は「スタイ」。。。らしいですが
それに続いて比較的作る人が多そうなのが「おくるみ」。
ランチョンマットとかコースターとかのように
布2枚を中表に縫い合わせればほぼ完成!という手軽さゆえでしょう。

サイズは90センチ四方、
頭入れるっぽいところ用に
22センチの正方形を三角に折ったものを取り付けてみた。
そこに縫いしろ1.5センチを見ておく。
そうやって裁断して
三角形を挟み込んだ上で中表に縫い合わせる。
表に返しておさえミシンして・・・
・・・なんと単純!
なのですが、意外と苦戦したのが布選びと裁断です。
どういうのがいいのか?と考え出すといろんなパターンがあって
決められず。
薄すぎても厚すぎてもいけない?
結局は、赤ちゃんに触れる方をワッフル生地にして
表面はWガーゼにしました。
どちらも、ネットで購入。(ガーゼ生地って可愛いのはなかなか店頭にない)
どちらもあらかじめ水通しをしておきます。
届いたばかりのガーゼは、ホントにガーゼ?って不安になるような
ごわつきがあって驚きましたが
水を通すとフワフワになりました。よかった。
で、地味に苦労したのは、ワッフル生地の裁断。
凸凹があって、うまく線がひけないのです。
新聞紙で90センチ四方の正方形を作って、
それをマチ針でとめて縫いしろ多めに見て雑に裁断して、
結局は比較的キレイに裁断できたガーゼ生地と合わせた後に
余分な縫いしろを切り落とすという荒技でしのぐ。
そもそも、こういうシンプルな正方形とか長方形のモノを作る場合、
普通は型紙用意するのかな?それとも定規ではかるだけ?
・・・少なくとも、サイズが大きくなる場合は
やっぱり簡単な紙切れでもいいので
型紙があった方がやりやすい!というのが私の結論です。
適量の返し口を残して中表で縫ったあと、表に返すのですが
縫いしろを両サイドに割ってちゃんとアイロンをかける、
というのが実は大切だと気付く。
そして返し口は手縫いで「コの字」縫い。(←意外と手芸本には書いてないのだ!)
それから押さえミシン(←表から、縁のごく際部分をミシンで縫う)をかければ
一応完成!
・・・ここからついつい欲が出てしまう。
最初はパイピングしようかと思っていたのですが
頭のポケットにつけたレースが意外と気に入り
ナチュラルな感じのレースで縁取ることに。
90センチ四方なので結構な長さが必要です。
レースの継ぎ接ぎの仕方は謎だらけで
仕上がりもギリギリという感じですが何とかできました。
中表に縫うという技法にちなんで
オムツ替えで使えそうなシートも作ってみました。

45センチ×70センチ。
同じくワッフル生地に、こちらはナイロン生地(エコバッグのようなイメージ)を合わせて防水(?)に。
こちらは王道の、バイアステープでパイピング。
レース縫い付けるより、やり方が色々検索できるのもあって
苦戦しなかったな・・・。
いや、パイピングは以前練習したからかな?
単純作業でも、やってみると本には書かれていないような
細かい疑問が実はでてくるものです。
そこは試行錯誤の繰り返し。
とりあえず出来てよかった!という安堵はもちろんのこと、
ソーイングについてまたひとつ勉強になりました、
という思いです。
sachiko
2017年02月26日
変化の今年をどう乗り切るか。
独立と同時に家族が増えることになりそうで、非常にワクワクしている。
と同時に、もちろんいろいろ心配ごとも。
とにかく第一に、今年の家計が心配。
もう、非常に心配だ。
当然、りんご農家の収入は、りんごを売らないと入らない。
りんごが売れるのは速いもので晩夏。メインは10、11月だ。
新規就農者の味方で、もちろん俺も申請予定の青年就農給付金という農水省のありがたい補助金は、スムースにいったとしてもすぐに入って来るわけでは無さそう。(当たり前だ。)
家計的に、今年をどう乗り越えるかが勝負だ。
しっかり真剣に農作業(しかも、独りでやるのは初めて!)に打ち込んで、売れるりんごを作りつつ、子育て(こっちも、初めて!)。
重なるときは重なるものだ。
しかし、同世代で子育てしつつ農作業をがんばっている仲間の話を聞けば、子どもがいることで、いなかったとき以上に頑張れるのだという。
まだ会ったこと無いけれど、そんな気もする。
貯金も心配になってきたので、融資も視野に入れて経営計画を立てている今日この頃だ。
然
2017年02月25日
2016年のBi-axis苗作りは、厳しい結果に。。。
りんごには様々な育て方があるのだけれど、昨年から実験を始めたBi-axis樹形ってのは、日本では本当に新しい技術で、実施している人はほんの僅か。
早期多収性が期待できる点や、高密植わい化栽培で使う台木よりも凍害に強い台木が使えそうで、苗の本数が少なくできて経済的な点など、上手くいったらなんだか良さそうなので、ちょっと実験してみているのだ。
近所のまるちゃん農園・中島さんが数年前から取り入れていて、参考にさせてもらっている。
昨年はスタートなので、苗作りから。
まあなんとなく思ったようにできたものもあった。

この左側は、2軸が100cmほど伸びてくれた。みんなこんなならいいのに!
作っていた苗が、約70本。
その中で、甘い目で見て、なんとなくうまくいったかな。来年次の段階にいけるかな、というのが15本程度。
。。。20%て。。。
なさけない。
苗作りの管理をきちんとできなかったのが要因だ。
灌水(水やり)と、草退治が甘かった。
灌水の回数は足りなかったと思うし、草は苗の周囲20cmくらいは手でむしってはいたのだが、その周りはときどきビーバーで刈るくらいだった。

(初夏)
ずっとこんな感じだったかな。
まわりの草に養分をとられていたのかもしれない。
来年は、要改善!
更にずくを出さねばならぬ。
そもそも、Bi-axis樹形とはなんぞや。
超単純に説明すると、
1、苗の段階で同じ長さの2軸をもつ苗木をつくる。
2、2軸それぞれを、高密植わい化栽培の1本のように使って生産。

※イメージ
期待されるメリット
●2軸あるため、樹勢を抑えられる。→肥沃地での利用や、凍害対策で、M9よりも強い台木の利用が可能。
●2本の軸に短い枝が多数出やすい。→高密植栽培と同じ多収性、作業性。
●高密植栽培よりも樹間が広い。→初期費用が圧縮できる。
来年は、うまくいった20%の子たちをどうやって2軸同じくらいの強さで伸びてもらうかを検証する。
同時に、うまくいかなかった子たちを再び2軸にするために、切り戻したりしてみる予定。
苗も新しく作ってみたいと。
そういえば、台木注文してないから、しないと。
然
2017年02月24日
日記帳のこと
結婚して以来、ゆるーく日記を書き続けています。
続けるコツは、「毎日」ではなく「ほぼ毎日」(ほぼ日刊トイみたいですね)
を目指すこと、そしてたとえしばらく日が空いても
気にせず臆せずとりあえずやめずに書いてみること。
結婚して3年が過ぎ、日記帳も3冊目が終盤に差し掛かっております。

1番右のが今の日記帳でちょうど1年くらい前から書き始めております。
ZENは3年日記を利用しており(それももうすぐ終わる)
3年分の今日を比較できるようになっているらしい。
私はその日書きたい量を書きたいぶんだけかけるように
普通のノートを活用。
数行のときもあれば2ページに及ぶこともあります。
基本的に右のページに文章を書き、
左側にはその時行った場所のカードとか
いただきものをしたときの誰かのメモとか手紙とかを貼ってます。
そういう意味では、結構いろんな方が登場します。
私にメモなどを渡す時は注意しておかないと
それが殴り書きであっても結構な確率で保管されてしまいます。
ちょっとしたこだわりは「カキモリ」さんのいいノートを使っていること。
1冊目は友人がくれたもので、
それを日記帳にしてみたところ習慣になり
東京に行けるときがあればノートをオーダーして・・・
というちょっと「特別」な感じを味わっております。
ブランド志向ではないけれど(我が家はそんな余裕もないし!)、
モノにこだわりを持つというのは贅沢な気分が味わえていいものですね。
さてさて、肝心な日記の中身ですが
そんなに波瀾万丈な毎日を過ごしているわけではないので
1日の流れを書いている程度。
それに夫婦の健康/精神状態を書き加え、
(ZENの疲労度合いも書いてあるので、農作業の日誌と合わせてみると面白い)
その頃ぼんやりと考えていることを書き
読んでいる本のことを書き
いつの頃からかその日作った料理の献立を書くようになり、
気付けば朝の味噌汁を作ったかどうかが
その日の私の調子の指針になっており(!)、
さらに気付けば味噌汁の具も書き記すようになっており・・・
・・・どれだけ味噌汁に執着しているのか。
無意識の習慣って怖いものです。
読み返せばなかなか面白いもの。
寝る前に読み返して結構笑えます。
誰に見せるでもない、自分だけの贅沢な日々の積み重ね。
以上、何となく日記のススメでした。
sachiko
続けるコツは、「毎日」ではなく「ほぼ毎日」(ほぼ日刊トイみたいですね)
を目指すこと、そしてたとえしばらく日が空いても
気にせず臆せずとりあえずやめずに書いてみること。
結婚して3年が過ぎ、日記帳も3冊目が終盤に差し掛かっております。

1番右のが今の日記帳でちょうど1年くらい前から書き始めております。
ZENは3年日記を利用しており(それももうすぐ終わる)
3年分の今日を比較できるようになっているらしい。
私はその日書きたい量を書きたいぶんだけかけるように
普通のノートを活用。
数行のときもあれば2ページに及ぶこともあります。
基本的に右のページに文章を書き、
左側にはその時行った場所のカードとか
いただきものをしたときの誰かのメモとか手紙とかを貼ってます。
そういう意味では、結構いろんな方が登場します。
私にメモなどを渡す時は注意しておかないと
それが殴り書きであっても結構な確率で保管されてしまいます。
ちょっとしたこだわりは「カキモリ」さんのいいノートを使っていること。
1冊目は友人がくれたもので、
それを日記帳にしてみたところ習慣になり
東京に行けるときがあればノートをオーダーして・・・
というちょっと「特別」な感じを味わっております。
ブランド志向ではないけれど(我が家はそんな余裕もないし!)、
モノにこだわりを持つというのは贅沢な気分が味わえていいものですね。
さてさて、肝心な日記の中身ですが
そんなに波瀾万丈な毎日を過ごしているわけではないので
1日の流れを書いている程度。
それに夫婦の健康/精神状態を書き加え、
(ZENの疲労度合いも書いてあるので、農作業の日誌と合わせてみると面白い)
その頃ぼんやりと考えていることを書き
読んでいる本のことを書き
いつの頃からかその日作った料理の献立を書くようになり、
気付けば朝の味噌汁を作ったかどうかが
その日の私の調子の指針になっており(!)、
さらに気付けば味噌汁の具も書き記すようになっており・・・
・・・どれだけ味噌汁に執着しているのか。
無意識の習慣って怖いものです。
読み返せばなかなか面白いもの。
寝る前に読み返して結構笑えます。
誰に見せるでもない、自分だけの贅沢な日々の積み重ね。
以上、何となく日記のススメでした。
sachiko
2017年02月23日
Bi-axis試験栽培、途中経過を発表しました
果樹研究会中信支部の研究発表大会で、
Bi-axis樹刑を用いた密植栽培トライアル~1年目~
と題してプレゼン。
まだ苗を作り出した段階だから、ねらいや今後の展望などを話し、2016年の試験経過を報告した。

新しい技術なので興味を持った会員も多かったようだ。
今後の報告を期待していただいた。
しっかりせねば。
そしてプレゼンは難しい。
頭の中で文章が組たたらない。
原稿が無い部分も、順序立てて話せるようになりたいわあ。。。
然
Bi-axis樹刑を用いた密植栽培トライアル~1年目~
と題してプレゼン。
まだ苗を作り出した段階だから、ねらいや今後の展望などを話し、2016年の試験経過を報告した。

新しい技術なので興味を持った会員も多かったようだ。
今後の報告を期待していただいた。
しっかりせねば。
そしてプレゼンは難しい。
頭の中で文章が組たたらない。
原稿が無い部分も、順序立てて話せるようになりたいわあ。。。
然
2017年02月22日
農業。厳しいけれど、あたたかい世界。
2月3日に書いた「刺激を受けるのは大好物なんだけれど、立ち止まって考えてみた。」は、結構たくさんの方が読んでくれたようで、数人の仲間や先輩生産者から反応をいただくことができた。
自分のfacebookではシェアしたのだが、なぜか昨日になって、アドバイスいただいた会津さんやY君(なぜか名前伏せててごめんw他意は無い。)がfacebookでシェアしてくれた。
彼らの農業者仲間が読んでくれたのだろう。
会津さんは、ご自身のブログでも触れていただいた。
ありがとうございます。(拡散してどうのということは無いのだけれど。)
反応の中で多かったのが、「自分も同じことで悩んでた!」という就農して日が浅い方の声や、「俺もそうだったよ〜。心配するな!」という先輩方の声だ。
みんな同じような葛藤を経て、自分のスタイルを作っている。
そんな経験をしているからこそ、外の活動を絞り込んで自分の生産に集中する後輩農業者のことも、“仲間”としてずっと応援してくれるんだ。
ひとりひとりが経営者で独立していても、応援し合っている。
農業って、厳しいけれど、あたたかい世界なのかも。
そんな世界でがんばれるってことは幸せなことだ。
今後がさらに楽しみになった。
「輝いている人は、外に出ているから輝いている。時間を作るのも経営者の仕事」というアドバイスもいただいた。
その通りだ。
今までのままだと、外に出て刺激をもらい、自分の目指すスタイルに向かうために、今後も時間を削ってしまうことになっていたかもしれない。
時間は削るものではなく、作るものなんだ。
肝心の農作業にかける時間は守りつつ、努力と工夫で、時間を作る。
その時間を使って、自分のスタイルを作っていく。
刺激をもらうために時間が無くなって困る。。。というのは、順番が逆なのだ。
いろいろな声をいただくことができ、本当に嬉しかった。
ありがとうございました。
俺も刺激を与えられる、みんなを応援できる人間になれるよう、まずは足元からがんばろう。
これからもよろしくお願いいたします。
然
2017年02月21日
ベビーミトンを作ってみた
前からやろうと思っていたこと、刺繍。
先月くらいから徐々に始めてみたところ、
普通のソーイングより性に合っている気がします。
しおりとかアクセサリーとかに仕立てるにもなかなか良いだろうし。
どうせ刺繍の練習をするならばベビー用品に使えそうなガーゼに
刺繍を施そう・・・と思った結果、
ベビーミトンができました。

「クジャク(羽広げてないけど)」と「花(食虫花っぽい)」のイメージ。
図書館で借りてきた本に載っていました。
なぜそのモチーフを選んだのか、自分でもわからない。
目の粗いガーゼに刺繍をするには、
裏にアイロンで接着芯を貼ると良いことを学ぶ。
快適に刺繍ができます。
裁断してから刺繍を施し、その後裏布と表布を合わせて縫うのですが
ベビー用品の作りって本当によく考えられている・・・。
いろんな本を見るとやたら「手縫い」が多いのは
ベビー用品手芸をする人が初心者だからとか
品物ひとつひとつが小さいので大して手間じゃないからだとか
そう思っていたのですが、
ミシンでざっくり縫ってしまうと裏面に縫い目が出てしまうという理由もちゃんとあるようで。
(縫う箇所にもよりますが、ゴム口とかは手縫いが大事かも)
表布と裏布の重ね方も半信半疑で本の通りにやってみると
見事に縫い目が裏に出ない!
通常のカバンとか大人の服ではやらない・・・素人にはわからない重ね方でした。
でも、表にこれでもか!ってくらい刺繍の糸が出てるので
赤ちゃんがこれで顔を擦ってしまっては
本末転倒かも?
・・・という疑問はさておき
刺繍はなかなかいいもののようです。
お絵描きの感覚で楽しいし。
・・・本末転倒といえば
そもそもベビーミトンっているのかも疑問。
でも、端切れでできるくらい小さいので
ついつい気軽に作ってしまう。
sachiko
先月くらいから徐々に始めてみたところ、
普通のソーイングより性に合っている気がします。
しおりとかアクセサリーとかに仕立てるにもなかなか良いだろうし。
どうせ刺繍の練習をするならばベビー用品に使えそうなガーゼに
刺繍を施そう・・・と思った結果、
ベビーミトンができました。

「クジャク(羽広げてないけど)」と「花(食虫花っぽい)」のイメージ。
図書館で借りてきた本に載っていました。
なぜそのモチーフを選んだのか、自分でもわからない。
目の粗いガーゼに刺繍をするには、
裏にアイロンで接着芯を貼ると良いことを学ぶ。
快適に刺繍ができます。
裁断してから刺繍を施し、その後裏布と表布を合わせて縫うのですが
ベビー用品の作りって本当によく考えられている・・・。
いろんな本を見るとやたら「手縫い」が多いのは
ベビー用品手芸をする人が初心者だからとか
品物ひとつひとつが小さいので大して手間じゃないからだとか
そう思っていたのですが、
ミシンでざっくり縫ってしまうと裏面に縫い目が出てしまうという理由もちゃんとあるようで。
(縫う箇所にもよりますが、ゴム口とかは手縫いが大事かも)
表布と裏布の重ね方も半信半疑で本の通りにやってみると
見事に縫い目が裏に出ない!
通常のカバンとか大人の服ではやらない・・・素人にはわからない重ね方でした。
でも、表にこれでもか!ってくらい刺繍の糸が出てるので
赤ちゃんがこれで顔を擦ってしまっては
本末転倒かも?
・・・という疑問はさておき
刺繍はなかなかいいもののようです。
お絵描きの感覚で楽しいし。
・・・本末転倒といえば
そもそもベビーミトンっているのかも疑問。
でも、端切れでできるくらい小さいので
ついつい気軽に作ってしまう。
sachiko
2017年02月20日
テキトーデスクをまた作ってみた。今回は棚付き。
あと一ヶ月くらいしたら生活がガラッと変わるので、今は家の中のいろんなものの置き場所を見直している。
あ、実際はsachikoが見直してくれている。
そんななか、sachikoの作業スペースもお引越が必要となり、それに伴って机がひとつ欲しいということになった。
手軽な値段の机はしょーもないものが多い(どれだけ安いのを見ているのか)ので、作ることにした。
一昨年、PC用デスクを自作してみて、結構いい感じに使えているから、同じ要領で作ってしまえ、というわけだ。
それがこちら。
こいつはテキトーに作れるくせに、なかなかいい作り方だと思う。
結構しっかりしていて、丈夫さだけは、いい値段しそう。
なんてったって、木そのものの風合いが楽しめるのが、粋じゃないか。(手抜き)
» 続きを読む
2017年02月19日
赤ちゃん用手作り肌着の考察
徐々にベビー用品が充実してきた我が家。
あまり身近に乳幼児がいた経験がないので
いろいろ目新しいものだらけで新鮮な発見があるものです。
とにかくベビー用品1つ1つが小さい!
というのもそんな驚きの1つ。
何かを作ろう!と思ってもそんなに大変じゃないだろう・・・
という憶測がベビー用品手芸の取っ掛かりなのでしょう、きっと。
私もご多分にもれず簡単にハンドメイドに手を出し
慣れないソーイングに日々精進し
赤ちゃん用品を揃えるという当初の目的から少しズレて
もはやソーイングの勉強をしているような境地にいたっております。
というよりも、やっぱり素人仕事は垢抜けないもので
これではとても・・・という出来になってしまうので
勉強!と割り切ってしまった方がいいというだけのこと。
完成は二の次にして・・・。
その反省が「手作り肌着」です。

作りかけですが一旦断念しようかと(笑)。
肌着づくりでマスターした技術は
*まつり縫い
*おり伏せ縫い
*バイアステープの作り方
*ガーゼ生地は水通ししてから使う
などでしょうか。
何となく知っていたつもりのことだけど
1つ1つ確認しながらやるとやっぱり基本は大事ですね。
あとは基本的な針の進め方とかミシンの扱いとかは
当たり前ですが回数を重ねると上達してきているのが我ながら実感できて楽しい。
朝ドラの影響を受けてかあえて縫製は表に出し
裏面は余計な縫い目が出ないように注意してみました。
バイアステープ作りにいたっては、
眠っていた端切れが生き返るようで心ときめきました。
バイアステープ作りについてはレシピを記しておきたいほどの出来。
でも、ほかは何かと失敗の繰り返し。
ガーゼ生地はほつれやすく、裁断した端からほじゃけてきて
縫い代が全然足りない!という自体に陥ったり
袖下から裾にかけての緩やかなカーブの縫製がゆがんだり
バイアステープを袖にパイピングするのにものすごく苦労したり。
カーブ縫えた!と思ってたらバイアステープと本体が浮いていたり。
これらの反省を活かして完成させようとしたら、
「えりや袖にバイアステープなどはらない」ということになるのですが
そしてそれならたぶん、ここ数日の取組の成果もあってすぐに作れるようになっているのだろうけれど
ここでふと我に返るのです。
肌着ってそこまでして作るものかな?と・・・。
しかも出来はイマイチ。。。
ある程度数も揃ってはいるし。。。
絶対不可欠なものはプロに任せて賢く買い(すぐに小さくなるし)
作りたいものはもっとずっと使えるものの方がいいよな・・・と。
何が何でもてづくり教!みたいなハンドメイドばばあにはなりたくないし・・・と。
ベビー用品はあくまでも赤ちゃんを取り巻く「品物」であって
大事なのは赤ちゃんそものもをどう育てるかだよな・・・という
哲学にまで発展したり。
肌着と格闘して学んだのはそんなところです。
ハンドメイドは好きだけど、やっぱり性にあっているのは
必需品じゃなくてサブ的な遊び心があるものを作ること。
(服じゃなくて雑貨かな・・・。)
ほろ苦い思いを味わいながらも
勉強になりました。
でもね、これに懲りずに家の片付けなどなどと並行してまだまだいろいろ挑戦しますよ。。。
sachiko
あまり身近に乳幼児がいた経験がないので
いろいろ目新しいものだらけで新鮮な発見があるものです。
とにかくベビー用品1つ1つが小さい!
というのもそんな驚きの1つ。
何かを作ろう!と思ってもそんなに大変じゃないだろう・・・
という憶測がベビー用品手芸の取っ掛かりなのでしょう、きっと。
私もご多分にもれず簡単にハンドメイドに手を出し
慣れないソーイングに日々精進し
赤ちゃん用品を揃えるという当初の目的から少しズレて
もはやソーイングの勉強をしているような境地にいたっております。
というよりも、やっぱり素人仕事は垢抜けないもので
これではとても・・・という出来になってしまうので
勉強!と割り切ってしまった方がいいというだけのこと。
完成は二の次にして・・・。
その反省が「手作り肌着」です。

作りかけですが一旦断念しようかと(笑)。
肌着づくりでマスターした技術は
*まつり縫い
*おり伏せ縫い
*バイアステープの作り方
*ガーゼ生地は水通ししてから使う
などでしょうか。
何となく知っていたつもりのことだけど
1つ1つ確認しながらやるとやっぱり基本は大事ですね。
あとは基本的な針の進め方とかミシンの扱いとかは
当たり前ですが回数を重ねると上達してきているのが我ながら実感できて楽しい。
朝ドラの影響を受けてかあえて縫製は表に出し
裏面は余計な縫い目が出ないように注意してみました。
バイアステープ作りにいたっては、
眠っていた端切れが生き返るようで心ときめきました。
バイアステープ作りについてはレシピを記しておきたいほどの出来。
でも、ほかは何かと失敗の繰り返し。
ガーゼ生地はほつれやすく、裁断した端からほじゃけてきて
縫い代が全然足りない!という自体に陥ったり
袖下から裾にかけての緩やかなカーブの縫製がゆがんだり
バイアステープを袖にパイピングするのにものすごく苦労したり。
カーブ縫えた!と思ってたらバイアステープと本体が浮いていたり。
これらの反省を活かして完成させようとしたら、
「えりや袖にバイアステープなどはらない」ということになるのですが
そしてそれならたぶん、ここ数日の取組の成果もあってすぐに作れるようになっているのだろうけれど
ここでふと我に返るのです。
肌着ってそこまでして作るものかな?と・・・。
しかも出来はイマイチ。。。
ある程度数も揃ってはいるし。。。
絶対不可欠なものはプロに任せて賢く買い(すぐに小さくなるし)
作りたいものはもっとずっと使えるものの方がいいよな・・・と。
何が何でもてづくり教!みたいなハンドメイドばばあにはなりたくないし・・・と。
ベビー用品はあくまでも赤ちゃんを取り巻く「品物」であって
大事なのは赤ちゃんそものもをどう育てるかだよな・・・という
哲学にまで発展したり。
肌着と格闘して学んだのはそんなところです。
ハンドメイドは好きだけど、やっぱり性にあっているのは
必需品じゃなくてサブ的な遊び心があるものを作ること。
(服じゃなくて雑貨かな・・・。)
ほろ苦い思いを味わいながらも
勉強になりました。
でもね、これに懲りずに家の片付けなどなどと並行してまだまだいろいろ挑戦しますよ。。。
sachiko